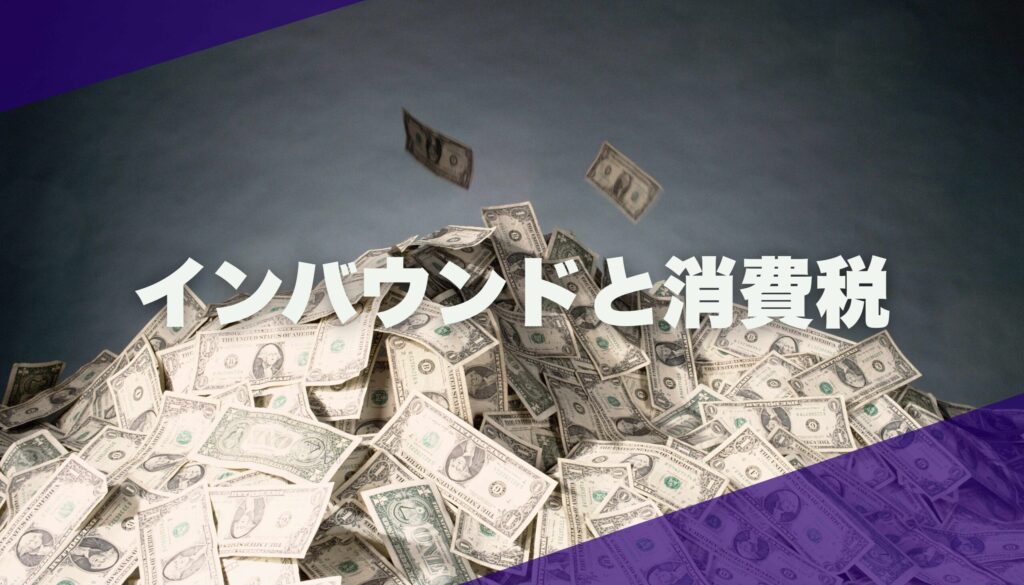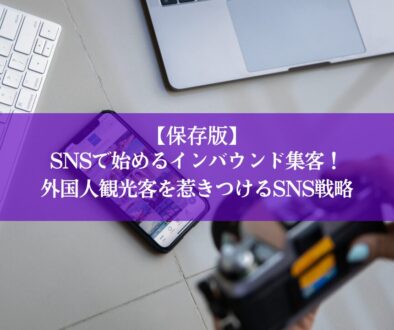外国人旅行者向け消費税免税制度の基本と改正動向:インバウンド対策の重要ポイント
目次
はじめに
「インバウンドと消費税」というキーワードを検索されたあなたは、外国人旅行者向けの「免税制度」が、単なる税務処理ではなく、集客戦略そのものと深く関連していることをご存知だと思います。特に、近年は「免税悪用」のニュースが相次ぎ、2025年度の税制改正で制度が大きく見直される動きがあり、現場の事業者には早急な対応が求められています。
私は長年、浅草の人力車店や忍者体験カフェの運営を通じ、インバウンドの消費行動と制度の狭間で多くの実務経験を積んできました。本記事では、この消費税免税制度の基本知識から、見直し後の「リファンド方式」への対応、そして免税販売ができない飲食店やサービス業者が取るべき代替「対策」まで、具体的なノウハウを解説します。
最新の情報をもとに、貴社のインバウンドビジネスを成功に導くための「必要」な「情報」を提供します。
1. インバウンド消費税免税制度の基本と必要性

1-1. 消費税免税制度の仕組みと対象
日本の消費税免税制度は、外国人旅行者などの非居住者が日本国内で商品を購入し、国外へ輸出することを前提に、消費税を免除する仕組みです。この制度は、日本の商品を海外に持ち帰ってもらうことで、インバウンド消費を促し、経済効果を増加させることを目的としています。
免税対象者:日本に滞在する期間が6ヶ月未満の外国人旅行者(非居住者)が主な対象です。(脚注1、6参照)
免税対象物品:一般物品(家電、衣料品など)と消耗品(食品、化粧品など)に分類され、それぞれに購入金額の要件が定められています。
免税店:免税販売を行うには、事前に税務署へ免税店としての届出と登録が必要です。
この制度は、訪日外国人にとっての価格的な魅力を高める上で非常に重要な役割を果たしてきました。
1-2. 飲食店や体験型サービスが「免税販売できない」理由
ここで注意が必要なのが、すべての業種が免税販売できるわけではないという点です。特に、飲食店や体験型サービスといった業種は、原則として免税販売の対象外とされています。
免税対象外の理由:免税制度の対象は「国外に持ち帰る物品」に限られます。飲食店での飲食や、忍者体験のような「サービス」は、日本国内で消費・享受されるものであるため、消費税の免除の対象とはなりません。(脚注5参照)
つまり、物品販売を目的としない事業者は、制度の恩恵を直接受けることはできませんが、だからこそ「付加価値の高いサービス」で集客する戦略が「必要」になります。(これについては後の章で解説します。)
2. 免税制度の見直しと不正利用という問題点

2-1. 高額商品の不正転売問題と「リファンド方式」への移行
近年、免税制度を悪用した不正転売が大きな社会問題となっています。訪日外国人が高額なブランド品などを免税で購入し、日本国内で転売して利益を得るケースが多発しました。(脚注7参照)
この「問題」の「解決」に向け、政府は2025年度税制改正で、現行の免税制度を抜本的に見直す方針を示しました。
リファンド方式への一本化:2026年を目途に、現在の店頭で消費税を引く方式(タックスフリー)から、一旦消費税込みの価格で販売し、出国時に空港などで税金を「還付」(リファンド)する方式への一本化が進められています。(脚注1、8参照)
不正対策の強化:高額商品を購入した際の購入者情報提供義務や、税関での確認強化などが導入されます。
この改正は、事業者にとって「対応」の負担を増加させることになりますが、制度の信頼性を回復し、持続的なインバウンド消費を促すためには「必要」な流れです。
2-2. 飲食店・サービス業者が取るべきインバウンド対策の「代替策」
免税制度の恩恵を直接受けられない飲食店や体験型サービス事業者こそ、デジタル技術を活用した集客対策が重要です。私は浅草の人力車店で、物品販売ではないサービスでも集客効果を上げるノウハウを確立しました。
MEO(マップエンジン最適化)対策の強化:外国人観光客はGoogleマップで「今いる場所の近くの店」を検索します。多言語での店舗情報、サービス内容、魅力的な写真、そして最新の営業時間を「提供」し、予約への導線を整備することが、免税分を上回る集客効果を生みます。
多言語Webサイトでの「体験」発信:忍者カフェの例のように、単なるメニューではなく、「ここでしか得られない体験」を多言語のWebサイトやSNSで発信します。価格的な魅力に頼らない「価値」を伝えることが、外国人旅行者の消費を促す鍵です。
モバイル決済の導入:不正防止のため「リファンド方式」への移行が進む中、キャッシュレス決済は必須です。主要国のモバイル決済に「対応」することで、利便性を高め、顧客体験を「改善」します。
3. 免税制度改正後の実務対応とMILOKUの支援
3-1. 免税販売事業者が今から準備すべき実務対応
2026年以降のリファンド方式への移行を見据え、免税販売を行う事業者は、今から以下の実務対応を進める必要があります。
新しいシステムへの移行計画:リファンド方式に対応したPOSシステムや、税関への情報提供を行うための「システム」の導入または更新を検討します。
顧客への丁寧な案内:制度変更に伴い、外国人旅行者が混乱しないよう、購入時に新しい方式や手続きについて多言語で分かりやすく「解説」するマニュアルを作成します。
国際的な税務コンプライアンスの確認:不正転売問題の背景には、国内の免税販売手続きの甘さも指摘されています。税務コンプライアンスを強化するため、専門家と連携して「業務」フローを「見直し」ます。
3-2. MILOKUによるインバウンド消費税対策と集客支援
消費税免税制度は今後変わりますが、インバウンド消費の需要が続くことは間違いありません。この変化の時期こそ、デジタル集客戦略を「強化」する絶好の機会です。
私たち株式会社MILOKUは、インバウンド対策のプロとして、煩雑な制度改正への対応を支援するだけでなく、貴社の「サービス」を日本国内だけでなく海外へも効果的に発信する戦略を「提供」します。
多言語WEBサイト制作、SEO・MEO対策、SNS運用といったあらゆる角度から、免税の有無に関わらず、外国人観光客を集客し、貴社の経済活動を支援します。免税制度の見直しに関するご相談や、デジタル集客戦略についての無料資料をご希望でしたら、今すぐお問い合わせください。
Q&A(よくある質問)
Q1. 免税制度の対象となるのはどのような物品ですか?
A1. 一般物品(家電、衣料品など)と消耗品(食品、化粧品など)があり、それぞれに購入額の要件があります。日本国内で消費されるサービスや飲食は対象外です。
Q2. 2026年に免税制度が改正されると、何が変わりますか?
A2. 店頭での免税が廃止され、リファンド方式(出国時に税が還付される方式)に一本化される予定です。これにより、不正転売問題の解決が期待されています。
Q3. 免税店の登録はどこに申請すればいいですか?
A3. 店舗を管轄する税務署に申請し、許可を受ける必要があります。申請手続きや要件は国税庁サイトで確認できます。
※本記事は、株式会社MILOKU 代表 川名の現場経験と最新の公開情報を基に執筆されました。
(脚注1:外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し~2025年度税制改正大綱 https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/r070127)
(脚注2:訪日外国人の免税制度はなぜ必要?最新動向と課題を超わかりやすく解説します! https://kankou-one.com/tax-free-system/)
(脚注3:「ショッピング目的の外国人観光客が減るかも…」自民党がインバウンド客の消費税の免税廃止を検討で、来日中の外国人たちの本音は https://news.yahoo.co.jp/articles/e7ef4e8a9286da06b7e75eed2b041cacc05f260e)
(脚注4:外国人旅行者の消費税免税措置の廃止を https://www.nakanishikenji.jp/blog/35323)
(脚注5:飲食店や体験型サービスは免税販売できる?その理由を解説! https://pievat.com/japan/merchant-blog/service-restaurant)
(脚注6:No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm)
(脚注7:免税悪用、訪日客1人で13億円分購入 消費税払わず出国 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE22D7W0S4A021C2000000/)
(脚注8:外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しと対応策 https://www.smc-g.co.jp/topic/ct07/consumption-tax-exemption/)